時代が変るということ
それは、何よりもまず「価値観が変わる」ということなのだと思う。
価値観とは、私たちが“正しい”と信じていることや、“当たり前”と感じていることの集合である。
その価値観が変われば、同じ出来事を見てもまったく違う解釈が生まれる。
つまり、「価値観の変化」とは、この世界の見え方そのものが変わるということに他ならない。
小さな世代間ギャップ、大きな文明の転換のヒント

たとえば、親世代と子ども世代で、ものの考え方がまるで違うと感じたことはないだろうか。
「昔はこうだったのに」「今の若い人は…」という言葉には、微妙な価値観のズレが浮かび上がっている。
それは一見、小さな違いに思えるかもしれない。
しかし、そうした違いが何世代も積み重なることで、やがて大きな時代の転換へとつながっていく。
価値観の変化は、突然に起こるのではなく、少しずつ、しかし確実に、社会の基盤を組み替えていくのだ。
日本における価値観の転換点

日本において、明確な価値観の転換が起こったと感じられる時代のひとつが、太平洋戦争の前後であろう。
戦前の日本では、「忠君愛国」や「滅私奉公」といった集団や国家への献身が美徳とされていた。
しかし、敗戦を経てGHQによる占領政策が実行される中で、それまでとは正反対ともいえる西洋の価値観が、日本社会の根底に据えられるようになった。
民主主義、個人の自由、平等、基本的人権の尊重――これらは、戦前の価値観とは対照的であり、国のあり方や人々の思考様式に深く影響を及ぼしてきた。
ここで太平洋戦争における日本の是非を論じるつもりはないが、ただひとつ心に留めておきたいのは、歴史とは「勝者が記録するもの」であるということだ。
ゆえに、敗者の論理はしばしば否定され、表舞台から消されていく。その過程で、新たな価値観が意図的に植え付けられるということも、現実として起こり得る。
時代は自然に移ろうように見える。
けれど、誰かの意図によって時代の“方向性”がつくられることもある。そうした側面もまた、私たちが歴史を語るうえで忘れてはならない事実だ。
この部分を掘り下げることはここでは控えるが、価値観の転換には、作為と無作為の両方が作用しているという認識を持つことは重要だと思う。
もちろん、すべてが一夜にして変わったわけではない。
日本人の中には、変わらずに受け継がれてきた精神性――自然への敬意、内省を重んじる感性、人と人のあいだの“間”を大切にする文化――も確かに息づいている。
それでもやはり、戦後という大きな時代の節目は、“正しいこと”の基準そのものを根底から変えた転換点であったと言えるだろう。
歴史を振り返ると見えてくる“価値観の地層”

こうした価値観の変化は、何も現代に限ったことではない。
明治維新では、「武士の誇り」が「近代国家の市民」へと書き換えられた。
江戸時代の始まりでは、戦国の武勇が治世の知恵へと変わった。
さらにさかのぼれば、鎌倉時代においては、貴族社会から武家社会への価値観の交代が起こっている。
いや、それよりもずっと以前、人類が狩猟から農耕へと生活様式を変えたとき、人間は「自然と共に移動する存在」から「自然を管理する存在」へと価値観をシフトさせた。
その変化が、後の文明を形づくる最初の一歩になった。
常識が“非常識”に変わる瞬間
このように、価値観の変化は、文明の基盤そのものを塗り替える力をもっている。
かつて、「太陽が地球のまわりを回っている」と信じられていた時代があった。
それが「地球が太陽のまわりを回っている」と知らされたとき、人々は何を感じたのだろうか。
おそらく、その変化は一夜にして起きたわけではない。
最初は異端として否定され、やがて少しずつ受け入れられ、数世代が経った頃には、それが“常識”になっていた――そんな流れだったのではないか。
つまり、時代の渦中にいる私たちは、変化の只中にいることに気づきにくい。
それが当たり前になった頃には、すでに時代は別の時代へと移っているのだ。
テクノロジーが揺さぶる“内面の価値”

今、私たちが直面しているのは、まさにそうした「価値観の転換期」なのかもしれない。
テクノロジーの進化によって、生活は格段に便利になった。
しかしその一方で、情報があまりにも多すぎて、心が追いつかないと感じる人も増えている。
選択肢が多いことが苦しみになり、つながりすぎることで孤独が深まる。
技術の進歩が、人間の“内面”を静かに揺さぶっている。
多様性とは、正解が一つではないという気づき
現代では「多様性」という言葉を頻繁に耳にするようになった。
私はこの言葉を、「受け入れるか受け入れないか」といった態度の問題ではなく“正解は一つではない”という価値観の変容の兆しだと感じている。
世の中には、“多様性”という言葉を使って時代を動かそうとする作為的な空気もあるかもしれない。
しかしそれ以上に、私たちがこの言葉に反応する背景には、旧来の正しさが揺らいでいることに、無意識に気づいているからなのではないかと思うのだ。
では、何が変わろうとしているのか
これまで“正しい”とされてきたことが、“そうではない”と感じられるようになったとき――
それは、新たな文明の幕開けなのかもしれない。
今まさに変わろうとしている“正しさ”とは何か?私はそれが、「権利を主張すること」そのものにあるのではないかと感じている。
(第2章へつづく)

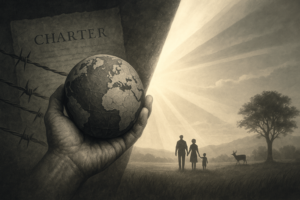








コメント