私たちは今、「権利」という言葉を日常的に使い、当たり前のようにその概念の上で社会を築いている。
表現の自由、所有権、労働の権利、教育を受ける権利――
それらは近代国家の礎であり、民主主義を支える根幹でもある。
けれど、ふと立ち止まって考えたくなるのだ。
そもそも、「権利」というものは、どうやって生まれてきたのだろうか?
権利の出発点とアングロサクソン文明の広がり
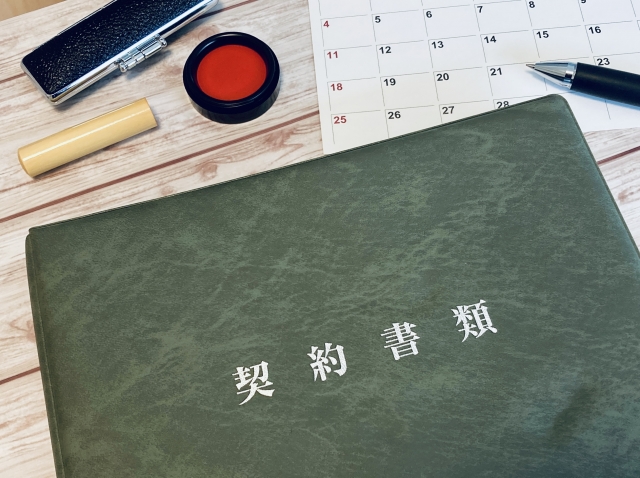
アングロサクソン文明――
それは「権利の主張」によって広がっていった文明だったと言えるかもしれない。
1215年、イギリスのジョン王が貴族の圧力のもとで署名した「マグナ・カルタ(大憲章)」は、王の権限を制限し、貴族階級の権利を保障するという画期的な出来事だった。
この一歩が、「権利を持つこと」によって支配から自由を得るという思想の始まりとなった。
以降、「権利の請願」や「権利の章典」、そしてアメリカ独立宣言やフランス人権宣言へとつながり、ついには、個人の権利が“国家の理念”になるまでに発展していった。
この流れを見ると、現代の政治制度や社会構造の大部分は、「権利を主張することで自由を勝ち取る」という前提の上に築かれていることがわかる。
権利の主張がもたらしたもの――侵略と支配

だが、もう一つの側面を見落としてはならない。
大航海時代、ヨーロッパ列強は世界各地へと進出し、土地の「所有権」を主張しては、次々と植民地化を進めていった。
その多くは、形式的な“契約”や“条約”という形を取り、「土地を譲渡した」とされてきた。
しかし、現地の先住民たちには、そもそも「土地を所有する」という概念自体が存在していなかった。
彼らにとって土地とは、共に在るものであり、誰かが支配する対象ではなかったのだ。
それでも契約書にサインがあれば、それは「権利の証明」だとされた。
こうして、理解も共有もされていない“所有”という価値観が、文明の名のもとに他者に押し付けられた。
それが、「権利の主張」のもうひとつの現実でもある。
現代社会における「権利」という前提

私たちが暮らす現代社会においても、「○○の権利」が次々と生まれ、それが正義として語られ、制度として広がっていく。
もちろん、私自身も、教育を受ける権利や、生活の権利によって守られてきた面は少なくない。
だから、権利そのものを否定することはない。
ただ、ここで問いたいのは、「権利を主張しなければ自由は得られないのか?」ということだ。
これは、アングロサクソン文明のロジックだ。
自由は“獲得するもの”であり、そのためには“主張”しなければならない。
主張しなければ奪われる――それが近現代社会の基本構造だとも言える。
権利の起源は「所有」にある

「権利」が生まれた背景をたどると、その源流にはやはり“所有”の概念があるように思う。
人類が狩猟から農耕へと生活様式を変え、定住するようになると、「この土地は自分たちのものだ」という意識が生まれた。
そして、それを守るために武力が生まれ、リーダーが生まれ、やがて国家や王政、貴族制度、身分制度が生まれていく。
土地の所有をめぐる争いは、やがて他人の権利を制限し、その制限に対して「私にも権利がある」と主張する動きが連鎖的に起こってきた。
つまり、「権利」とは本来、“奪われたものを取り戻す”ための道具として発展してきたのかもしれない。
けれど、本当に「所有」する必要があるのか?
だが、ここであらためて問い直してみたい。
そもそも、土地は誰のものなのだろうか?
地球に存在するあらゆる命は、
そこに“在る”というだけで生きている。
生まれてから死ぬまで、誰かの許可を得ることなく、自然と共に過ごしてきた。
大航海時代に侵略された多くの地域では、「所有」や「権利」という概念すらなかった。
それでも彼らは、自然の循環のなかで平和に暮らしていた。
もちろん、争いもあっただろう。
しかしそれは、現代のような“契約と権利に基づく支配”とは異なる、もっと原始的で本能的なものだったはずだ。
権利がなければ自由はないのか?
近代社会では、「権利がなければ自由がない」とされる。
だが、その逆はどうだろうか?
「主張しないと守られない自由」に、私たちは安心して生きられるのだろうか。
本当は、主張しなくても守り合える関係性のほうが、より自然で、より豊かな社会なのではないか。
地球に生きる私たちは、本来、誰のものでもないこの星を“共に使わせていただいている”という感覚で存在していたはずだ。
それは、「所有」ではなく「共有」――
もっと言えば、“共に在る”という意識に他ならない。
私たちは今、その意識を思い出すタイミングにあるのかもしれない。
(第3章へつづく)


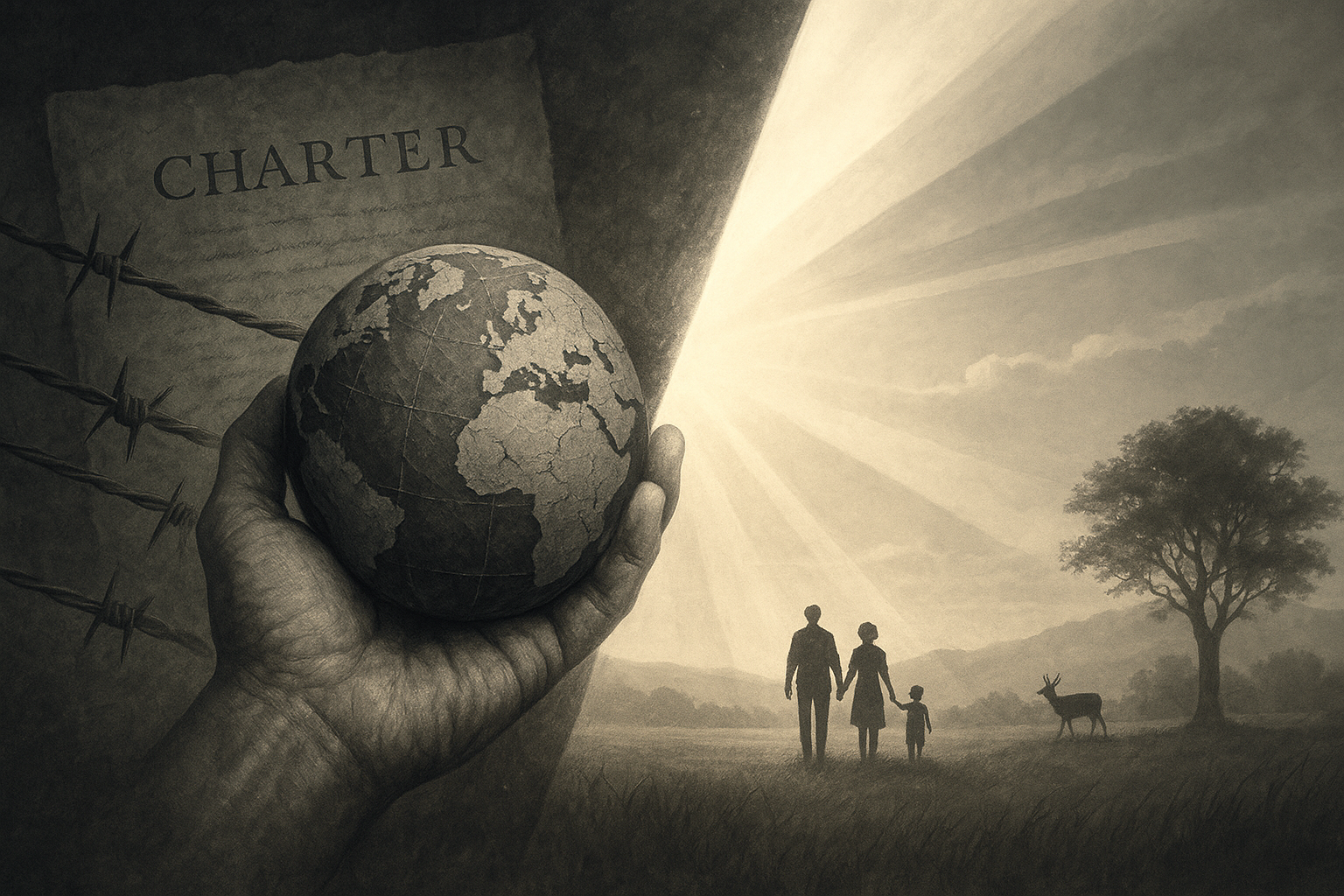






コメント